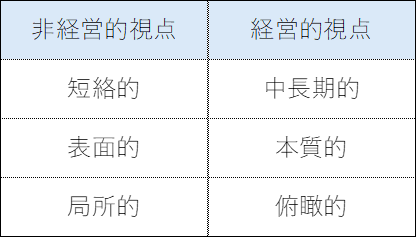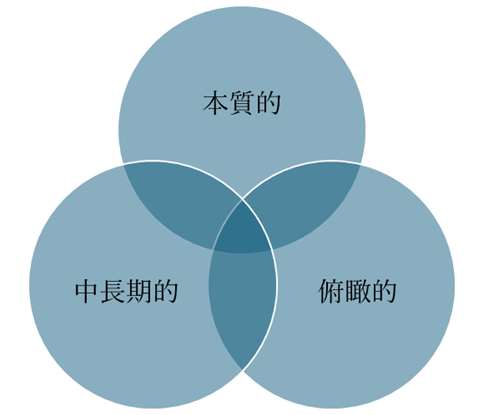右腕・後継者を育てるための“経営的視点”入門 ~①経営的視点とは?~
戦略的人事
中小企業の経営者なら、こんな思いを抱いたことがあるのではないだろうか。
・自分の右腕として頼れる人材が欲しい
・自分と同じ視座で話せる人材が欲しい
・自分の後継者と自信をもって言える人材が欲しい
一方で、こんな悩みもよく耳にする。
・プレイヤーとしては優秀なのだが…
・一部門の長としてはよくやってくれているのだが…
など「経営的視点」を持った人材の育成に頭を抱えている経営者は多い。
また、特に中小企業においては、「全社員が経営者」との意識をもって、
各社員が「経営的視点」をもって自律的に動いてくれると心強いものである。
本記事では、「経営的視点」を育むためのヒントを考えていきたい。
まず今回は、そもそも「経営的視点」とは何かについて解像度を上げてみたいと思う。
中長期的・本質的・俯瞰的に考える
例えば、「期待していた若手の社員Aさんが退職をしてしまった」という出来事が起きたとき、どんなことを考えるだろうか。
◻︎「来月のプロジェクト納期に間に合わない」(①)
◻︎「今四半期の売上目標が危ない」(①)
◻︎「給料が安いから辞めた」(②)
◻︎「上司と合わなかったから辞めた」(②)
◻︎「また人手不足で残業が増えてしまう」(③)
◻︎「とりあえず派遣社員で穴埋めしよう」(③)等々
ありがちな回答である。
経営的視点に立つと、
◻︎「このペースの採用・退職が続くと、5年後の事業拡大に必要な人材が確保できない。何か打開策はないだろうか?」(❶)
◻︎「本当に給料や上司だけの問題だろうか?」(❷)
◻︎「個人的な原因なのか?環境や制度に原因があるのだろうか?最近の退職の真因は何だろうか?」(❷)
◻︎「他部門も同様の離職傾向があり、全社的な構造的問題があるのだろうか?」(❸)
◻︎「競合他社と比較して、当社の働く環境に何が不足しているのだろうか?」(❸)等々
例えば、そんな問いがよぎるのではないだろうか。
この前者と後者の視点の違いは何だろうか。
それは、以下の通りである。
非経営的視点(前者)とは、「①短絡的、②表面的、③局所的」に考えているのに対して、
経営的視点(後者)とは、「❶中長期的、❷本質的、❸俯瞰的」に考えている。
つまり、この「中長期的、本質的、俯瞰的」に考えることができるかどうかが、経営的視点を育む上で重要なポイントとなる。
戦後の昭和で「歴代総理の指南番」とも呼ばれ、政官財界のリーダーに大きな影響力を与えた東洋思想家、安岡正篤氏の教えに「思考の三原則」というものがある。
○長期的思考:目先に捉われず、できるだけ長い目で見ること
○根本的思考:枝葉末節に捉われず、根本的に考えること
○多面的思考:物事の一面に捉われず、できるだけ多面的に見ること
まさに、ここでいう経営的視点と符号する。
大局的に判断する
さらに、もう一つ重要なことがある。それは、
「中長期的、本質的、俯瞰的」に考えていったときに、
・すぐには解決できない時間を要する課題
・核心的であるが多大なる労力やコスト・リソースがかかる課題
・各方面・各部門等多岐にわたる課題
などが明らかになってくる。
それらをもとに、効果性と実現性を踏まえ、的確に「優先順位」をつけて
重要な課題やその解決策に絞り込めるかどうかが問われる。
このことを「大局的に判断」するとここでは呼びたい。
この「大局的判断」ができないと、
単に正論を振りかざすだけになってしまい、
誰もついてきてくれなくなってしまうかもしれない。よくあることである。
折角「中長期的・本質的・俯瞰的」に考えて、適切に課題認識をしても、
事は前に進まなくなってしまう。
これでは本末転倒である。
だからこそ、「大局的判断」すなわち、効果性と実現性を踏まえ、的確に「優先順位」をつけて重要な課題やその解決策に絞り込むことが欠かせない。
ここまでまとめるならば、「経営的視点」とは、
「中長期的、本質的、俯瞰的に考え、効果性と実現性を踏まえて優先順位をつけながら、大局的に判断すること」と言える。
では、この「経営的視点」を育むためにはどうすればよいか、次回以降で深掘りしていくことにしたい。
※コラムは執筆者の個人的見解であり、人事戦略研究所の公式見解を示すものではありません。